氾濫原の概要については、

において、簡単に書いてありますので、
ぜひ見ておいてください。
今回は氾濫原について詳しく見ていきます。
三日月湖(河跡湖・牛角湖)
河川が山地から平野部に流れると、
勾配がなだらかになるため流れが遅くなっていきます。
山地においては、直線的な流路でしたが、
だんだん蛇行していきます。
より軟らかい地盤を削りながら流路を変えて、
少しずつ少しずつ蛇行していきます。
この蛇行をメアンダーともいいます。
洪水が起こると、水量が一気に増えます。
流路がまっすぐに短絡(ショートカット)されることもあります。
蛇行されていたこれまでの流路が切り離されると、
三日月湖になります。
自然堤防
河川が氾濫すると、水だけではなく、上流から運ばれてきた砂や泥なども
河川の外側に土砂が飛散します。
洪水時にあふれだした砂や泥などの堆積物は、
河川の両側に堆積して数10cmから数mの微高地を形成します。
微高地とは、周囲よりわずかに高い土地のことで、
この土砂の氾濫でできる微高地を自然堤防といいます。
自然堤防の土地利用
自然堤防は、微高地であるため水はけが良いため、水をためておく水田には向きません。
そのため、畑作や果樹園として利用されます。
さらに、周囲よりわずかに高い土地であるため、
洪水でたとえ水が川から溢れても低い土地へ流れていくため、
浸水被害が避けられるために、古くから集落が発達してきました。
この集落は川に沿ってできる自然堤防の上にあるため、
列状に発達しています。つまり列村が成立しやすいのです。
近年では道路や鉄道が整備されやすいです。
後背湿地
自然堤防の背後には広く低湿地帯が形成されます。
この低湿地を後背湿地といいます。
これは、洪水で河川からあふれだした水や粘土などが、
自然堤防に妨げられて河川に戻ることができないからです。
後背湿地は水もちの良い低湿地であるため、
水田として利用されることが多いです。

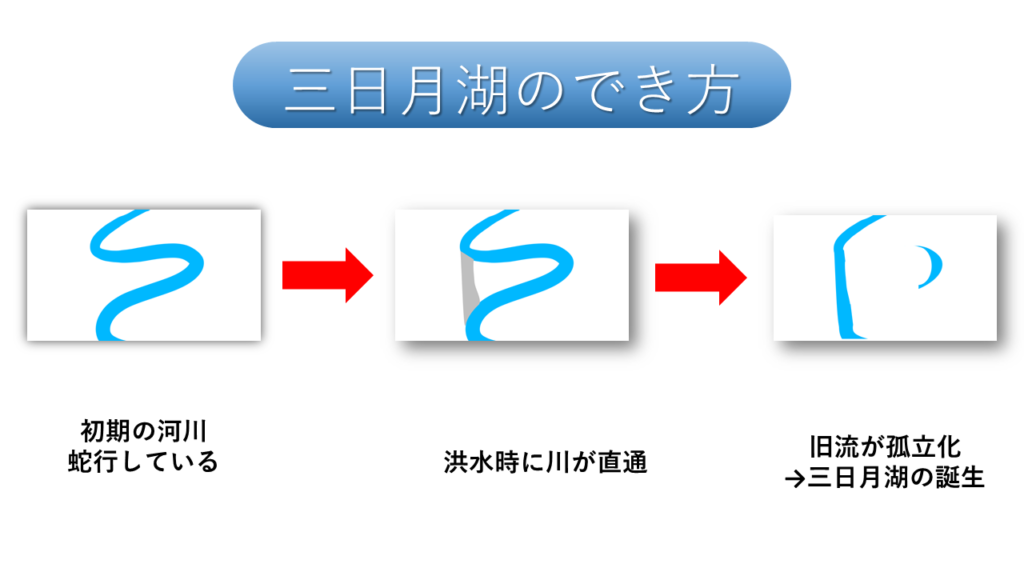


コメント