以前、お話しました
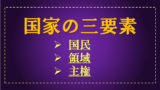
のうち、の領域について今回は詳しく見ていきたいと思います。
なぜなら領域は地理学的には大切だからです。
領域の分類
領域には、領土・領海・領空があります。
陸海空ですね。
領土とは?
領土とはどこまでをさすのでしょうか?
干潮時と満潮時では陸の幅がことなってしまいます…。
どこの国も領土は少しでも見栄をはってでも、
大きく言いたいわけです。
男の人は、男性器を大きく申告したいし、
女の人は、胸を大きく申告したいのと同じです。
そこで、干潮時の海岸線(低潮線)までの範囲を、
領土の範囲にしています。
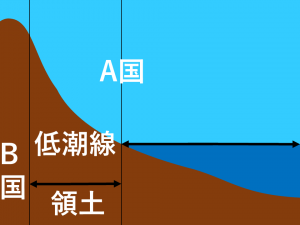
領土が広大な国
領土の面積が、
大陸全体を占めるような国を
大陸国といいます。
オーストラリアは、
一国で一大陸を占めているので、
典型的な大陸国といえます。
領土の面積大きい順
- ロシア
- カナダ
- アメリカ
- 中国
- ブラジル
- オーストラリア
- インド

です。
大きな3を書くと、
その順番で並んでいることが
わかるかと思います。
領海とは?
日本の領海は、
低潮線から12カイリのところまでです。
日本の領海は12カイリですが、
他国では、3カイリから200カイリまで、
幅広く設定されています。
公海とは?
領海とは逆に、
どの国のものでもない海を
「公海(こうかい)」といいます。
領海は沿岸国に属します。
ですので、
領海には許可なく他国の船が航海したり、
海底ケーブルを設置するのは禁止されています。
公海は、領有してはいけません。
ですので、公海は航海する自由があり、
海底ケーブルを置く自由があります。
もちろん領空もないので、
公海の上空を飛行機が通過してもかまいません。
公海の提唱者
公海は「公海自由の原則」といい、
H・グロティウス(1583~1645/オランダ)によって説かれた
国際法上の慣行を経て、確立されました。
経済水域とは?
経済水域とは、領海ではありません。
ですので、公海と同じように、
通過の自由や海底ケーブルの敷設の自由があります。
では、公海と排他的経済水域では一体なにが違うのでしょうか?
排他的経済水域では、
海の魚を捕獲すること、
海底のメタンガスやレアメタルなどの
資源を採取することについて、
経済水域では
その沿岸国が管理することが
認められています。
経済水域のはじまり
1973年、第三次国連海洋法会議で、
排他的経済水域が議題に上がりました。
そして、1982年には、
国連海洋法条約が採択されました。
それ以降、
多くの国が、経済水域を領土から200カイリ以内に設定しました。
日本は、始めは水産資源の管理だけに絞り、
「漁業専管水域」といっていましたが、
1996年に国連海洋法条約に加入し、
漁業専管水域から経済水域というようになりました。

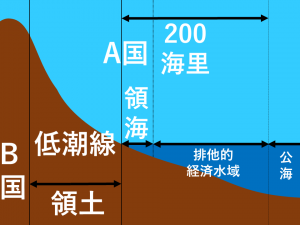


コメント